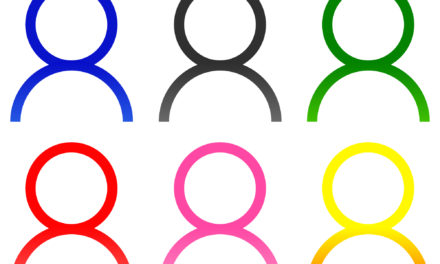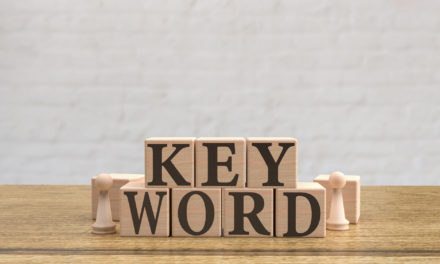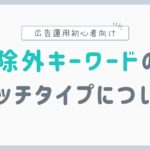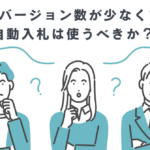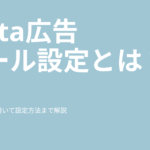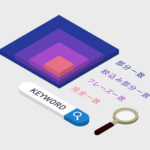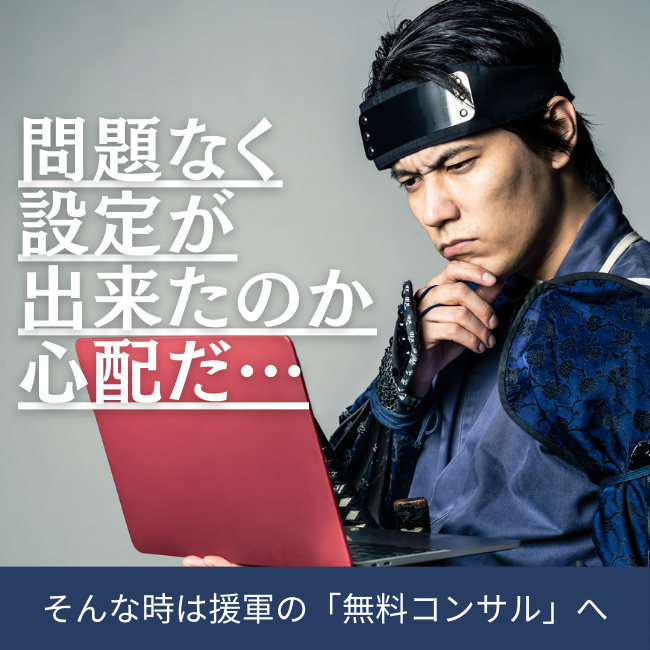Google広告でディスプレイキャンペーンの広告配信を行っている場合、一度は「ターゲットの拡張」機能を使用するかどうか検討したことがあると思います。この機能は、文字通り「ターゲットを拡張する機能」ですので、上手くいけば「表示回数の増加」「クリック数の増加」「コンバージョン数の増加」等の良い効果を得られます。しかしながら、このような良い効果は必ず得られるものなのでしょうか?
コンテンツ
結論:必ず良い効果を得られるわけではない
当たり前ですが、「ターゲットの拡張」機能を導入しても、必ずしも良い効果を得られるわけではありません。仕様の説明だけ読むと効果的に思える機能でも、実際に使ってみると思ったほどの効果が無かったり、そもそも全く効果が無かったりすることがありますが、それと同じです。そもそも100%確実に効果のある機能なんてものは存在しません。
失敗する場合のよくあるケース2つ
「ターゲットの拡張」機能ではターゲットの拡張を行う前の段階での「成果に繋がりやすいユーザー属性」と類似したユーザー層へ広告配信拡張を行いますので、この機能を導入する広告グループや広告アカウント自体にディスプレイ広告での多数のコンバージョン実績が計上されていない場合はこの機能が上手く動作する確率が下がります。
また、最近では自動入札機能を併用することが一般的かと思いますが、その場合は自動入札機能の影響により「機械学習の学習期間を経て成果が安定してくる」という挙動を示しますので、短期間で「ターゲットの拡張」機能の良し悪しを判断しようとすると「成果が安定する前に判断を下している」形となる為、その期間だけではこの機能が上手く動作する確率が高まらないでしょう。
失敗も覚悟の上で挑戦すべきではある
これまでの説明の通り、「ターゲットの拡張」機能を使用しても必ず良い成果に繋がるとは限りません。しかしながら、だからと言って「ターゲットの拡張」機能を使うべきではないということではありません。むしろその逆で、失敗を覚悟の上で「ターゲットの拡張」機能を使ってみることをお勧め致します。失敗する可能性があるからこそ、競合も「1度失敗するともうやめてしまう」ということがありえますので、「上手くいくまで挑戦し続ければ1人勝ちになる可能性もある」と考えることもできますよね。
今回は以上です。事業拡大を狙うなら、検索連動型広告だけでなく、ディスプレイ広告も活用できた方が明らかに有利となります。検索連動型広告は「検索行動をする見込客の数=コンバージョン数の限界」となりますが、ディスプレイ広告では「検索行動以外のインターネットを利用する全ての見込客(動画サイトや情報サイトを視聴・閲覧している全ての見込客)の数=コンバージョン数の限界」となり、ディスプレイ広告を上手に活用できた方がコンバージョン獲得数の最大化という点において圧倒的に有利だからです。今回お話した「ターゲットの拡張機能」含めてディスプレイ広告に関する機能を徹底的に活用し、上手くディスプレイ広告の広告運用を行っていきましょう!
Akira Kodaka
最新記事 by Akira Kodaka (全て見る)
- Google広告:サイト訪問者ではないユーザーにリマーケティング広告が表示されていそうだけど、なぜ? - 2024-07-25
- YouTube:初めて動画制作を行いますが、どんな動画を作ればよいですか? - 2024-07-16
- Google広告:目標コンバージョン単価入札の入札単価は毎日変更してよいですか? - 2024-07-10